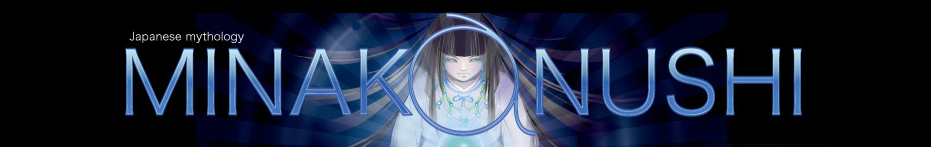
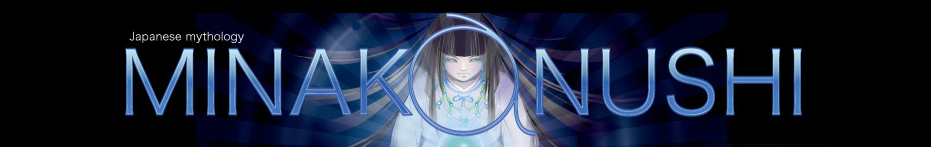 |
||
| |
||
| トリップ
24 2016/2/4 ルート履歴 |
|

社頭 はじめは社標の文字が読めなかった |
大阪・交野市の磐船神社を後にして168号線を南下、県道1号から富雄の方に向かうと三碓(みつがらす)と言う地域があり、そこに社叢を蓄えた小さな山がある。 |
||
 |
 |
||

石段を上がって正面に神楽殿 |

右が拝殿 |
||

恵美須神社 富雄のえべっさん |

英霊殿 地域の戦没者の英霊を祀る |
||

拝殿 中央が神門となる(中門) |

拝殿奥 ご本殿 |
||

ご本殿 五軒社流造り 国重要文化財 |
創起については延喜式以前より存在しており、古墳時代まで遡るとされる。 |
||

福神宮 |

福神宮 鳥見之庄の豪族・小野福麿公を祀る |
||

九之明神 小野福麿の九人の従者を祀る。 |

本殿東側奥 |
||

天香具山神社 |

伊勢神宮遥拝所 |
||

龍王神社 |

龍王神社 |
||

龍王神社より境内へ |
本殿の横に天香具山神社と龍王神社に連なる参道があり、ゆっくり歩いてみる事にする。龍王神社の背後に龍神の池があり社叢の中に静かに佇んでいる。
|
||

石段前にある石仏・地蔵(下)となり根聖院のものと思われる |
|||
 |
|
ー 表紙・古事記・日本神話・神道・神々・社寺探訪・日本国・ノベル・ブログ・桐の会 ー Copyright ⓒ Sakane. All Rights Reserved.
|