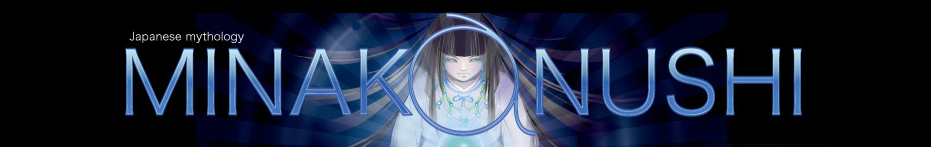
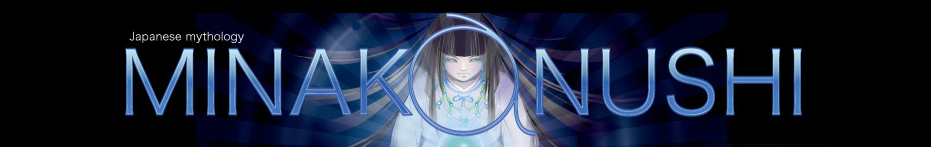 |
||
| |
||
| トリップ 17 2015/12/29 ▶ 京都・八幡市方面 |

道中にキウィを発見 鈴なりだ |
年の瀬も押し迫ってきたが、おそらく本年最後の参詣となるだろう。 |
||
 神社入口の鳥居 |
 ご由緒ではなく「定」 |
||
 |
薄暗い中、参道を進むと原始林に包まれたような中に、鳥居と拝殿が見えてくる。 |
||
 |
 |
||
 杜の中を参道が伸びる |
 拝殿 |
||
 ご本殿(左)右は八幡神社 ともに重要文化財 |
 垣外から見た本殿 |
||
 |
垣外に末社の天神社があり、神社の呼び名について本来は「かたのあまつかみのやしろ」が正しいが、「かたのてんじんしゃ」とも呼ばれるらしく、確かに天神様も居られるので、宮司様曰く、間違っているわけではないとの事。 |
||
 本殿横 |
 天神社 |
||
 本殿横 蛙股の彫刻 |
 拝殿横彫刻 宮司さんもよく分からないらしい |
||
 |
 |
||
 樟葉宮跡にある末社 貴船神社(穂掛神社) |
 継体天皇樟葉宮跡伝承地・大阪府指定史跡 |
||
 |
 |
||
 約1500年前ここに継体天皇樟葉宮があったとは・・ |
ひっそりとした中に佇む貴船神社で参拝し、少々感慨に耽りながら、次の目的地へと移動する。
|
||

北側に抜けた所に鳥居 |
|
ー 表紙・古事記・日本神話・神道・神々・社寺探訪・日本国・ノベル・ブログ・桐の会 ー Copyright ⓒ Sakane. All Rights Reserved.
|